今回は、前回のお話の続きです。
はじめに:
感謝って、そんなに簡単じゃない
「感謝しなきゃ…でも、なんかモヤモヤする」
「ありがたいって思いたいのに、心がついてこない」
「感謝日記?3日で飽きたよね〜」
そんなあなたに朗報です。
感謝って、そもそも“する”ものじゃないんです。
湧くものなんです。炭酸みたいに、ぷしゅっと。
でもその炭酸、栓が固くて開かないこともある。
この記事では、感謝が湧かない理由を心理学と脳科学でひも解きながら、
「ありがたさスイッチ」をオンにする方法を紹介します!
感謝ってなに?
(おさらい)
感謝とは、心理学的には「恩恵の知覚+ポジティブな情動反応」。
つまり、「あ、これありがたいかも!」って気づいて、「うれしいな〜」って感じること。
でもこの“気づき”と“感じる”って、意外と難しい。
なぜなら、脳はいつも忙しいから!
- スマホ通知に反応
- 明日の予定に焦り
- 過去の失敗を反芻(はんすう)
- ケーキを食べながら動画を観る(←これ後で出てくるよ)
脳の注意システムはスポットライトみたいなもので、
どこに向けるかで見える世界が変わります。
感謝は、スポットライトが「うれしいこと」に当たったときに湧く炭酸水。
注意が分散してると、炭酸は抜けちゃうんです。
感謝できない理由:
感謝の炭酸が抜ける7つのあるある
1. 受け取りモードになってない
ケーキを食べながらSNSを見てると、
「え、もう食べ終わった?味、覚えてない…」ってなるよね。
これは“味わい”が起きてない状態。
感謝は「受け取る→味わう→湧く」の順番だから、
受け取らないと始まらない!
2. 感謝すべきと思ってる(義務感)
「ありがとうは?」って言われ続けた子ども時代。
その結果、感謝=すべきこと、って脳が学習しちゃう。
でも、義務で感じる感情って、だいたい炭酸抜けてる。
3. 注意がズレてる(認知バイアス)
- ネガティビティバイアス:悪いことに目が行きがち
- ヘドニック・アダプテーション:良いことに慣れて“当たり前”になって見えなくなる
- プレッシャー:見返りを求められる不安で、素直に受け取れない
脳内では「ありがたい係」が少数派になってるかも。
4. 信用できない(トラウマ)
「親切の裏に何かあるんじゃ…」って思うと、ありがたさより警戒心が先に立つ。
これは防衛本能だから、責めなくてOK。でも炭酸は湧きにくい。
5. 罪悪感がある
「相手も大変なのに、もらっちゃって申し訳ない…」
この気持ち、やさしさの裏返しだけど、
感謝の炭酸にはフタをしちゃう。
6. 自己価値感が低い
「自分なんかが受け取っていいの?」って思うと、恩恵をキャッチするアンテナが折れちゃう。
まずはアンテナ修理から!
7. 恩恵に気づいてない
“当たり前”って、実は感謝の最大の敵。
失って初めて「ありがたかった…」ってなるのは、炭酸が冷蔵庫で眠ってたパターン。
感謝が湧く仕組み:
脳の炭酸ドリップ式
感謝って、いきなり「ありがた〜い!」って湧くわけじゃない。
実は、脳内ではこんな順番で起きてます:
- 注意を向ける(スポットライトを“うれしいこと”に)
- 恩恵として認識する(これは自分にとってプラスかも)
- 味わう(五感+内側の感覚でじっくり感じる)
- 情動が立ち上がる(うれしい!ありがたい!)
この流れ、まるでドリップコーヒーみたいでしょ?
お湯(注意)を豆(出来事)にゆっくり注ぐと、香り(感情)が立ち上がる。
急いでジャーッと注ぐと、ただのぬるま湯になるので注意⚠️
ちなみに、味わう力にはインターロセプションっていう専門用語があるよ。
これは「体の内側の感覚に気づく力」。
呼吸の心地よさとか、ケーキの舌ざわりとか、そういう“内なるセンサー”のこと!

感謝の方法:
炭酸を邪魔しないコツ
ここからは、感謝を“する”んじゃなくて、“湧くのを邪魔しない”方法を紹介するね。
ステップ1:
感謝=義務という誤解を外す
「ありがたいと思わなきゃ」は、炭酸の栓をねじ切る行為。
まずは「思わなくてもいいや〜」ってゆるめることが大事!
ステップ2:
うれしいことに注意を向ける
脳のスポットライトを「足りないもの」から「あるもの」へ。
たとえば、「今日のケーキ、見た目がかわいい」だけでもOK!
ステップ3:
味わう練習
スマホ通知をオフにして、ケーキを一口。
舌ざわり、香り、見た目、音(?)まで感じてみよう。
これが“感覚の炭酸”を立ち上げる秘訣!
ステップ4:
言葉にしてみる
「このケーキ、ふわふわで幸せ」って短く言語化すると、脳が「これは恩恵だな」とラベル付けしてくれる。
感謝の炭酸、ぷしゅっ!
押しつけ感謝の見分け方:
それ、炭酸じゃなくて圧力鍋かも?
感謝って、自然に湧くときは心地いいけど、押しつけられると「うっ…」ってなるよね。
それ、炭酸じゃなくて“圧力鍋”です。
ふた開けたら爆発するやつ。
押しつけ感謝のサイン
- 「ありがとうって言わなきゃ…」と焦る
- 感じてないのに“ありがたがるフリ”をする
- 「お返ししなきゃ」とプレッシャーを感じる
- 喜んで見せなきゃ、と演技モードになる
- 「感謝しないなんて非常識」と言われる(または自分で思う)
これらが出てきたら、いったん深呼吸。
それは“感謝のふり”であって、“感謝の気持ち”じゃないかも。
健全な感謝の特徴
- 自分のペースで湧いてくる
- 義務感より「うれしいな」が先にある
- お返ししたくなるけど、しなくてもOKと思える
- 「ありがとう」が自然に出る(出なくてもOK)
感謝って、自由でいいんだよ〜。
炭酸は勝手に湧くから、無理に振らなくて大丈夫!
よくある誤解と科学的注意点:
思い込みに炭酸を抜かれないために
誤解1:
感謝すればいいことが起きる
→ たしかに、感謝と幸福感には相関があるけど、「感謝=願いが叶う魔法」ではないよ。
科学的には、感謝は認知の視点を変える力。
現実を変えるというよりも、現実の見え方を変えるんだ。
誤解2:
ネガティブ感情はダメ
→ いやいや、ネガティブも大事!
危険を察知したり、自分を守ったりする大切なセンサー。
感謝と共存できるから、追い出さなくてOK!
誤解3:
感謝日記は万能
→ 書き方次第!
「今日は天気が良かった。ありがたい」だけだと、脳が「はいはい、テンプレね」ってスルーしちゃう。
味わいながら書くのがコツだよ〜!
まとめ:
ありがたさは、味わいの中に湧く
感謝は“する”ものじゃなくて、“湧く”もの。
そのためには…
- 注意を向ける
- 恩恵に気づく
- 味わう
- 無理にありがたがらない!
この流れを大切にすれば、
あなたの中の“ありがたさ炭酸”は、自然にぷしゅっと立ち上がるはず。
今日の1分ワーク:
炭酸スイッチON!
- スマホを置く
- 飲み物をひとくち
- 「これ、ありがたいかも」とつぶやく
- 舌ざわり、温度、香りを味わう
- ぷしゅっ(感謝発生)

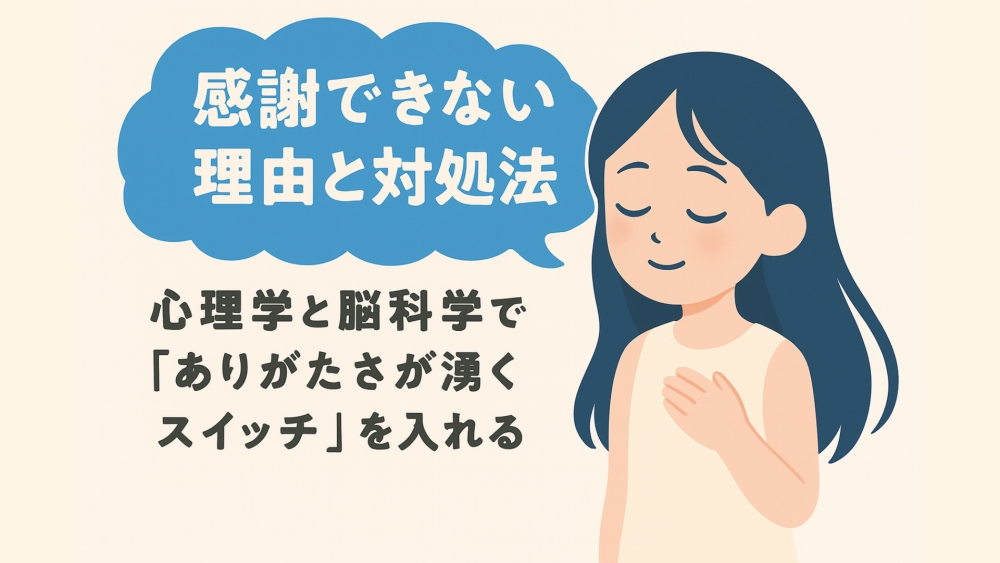
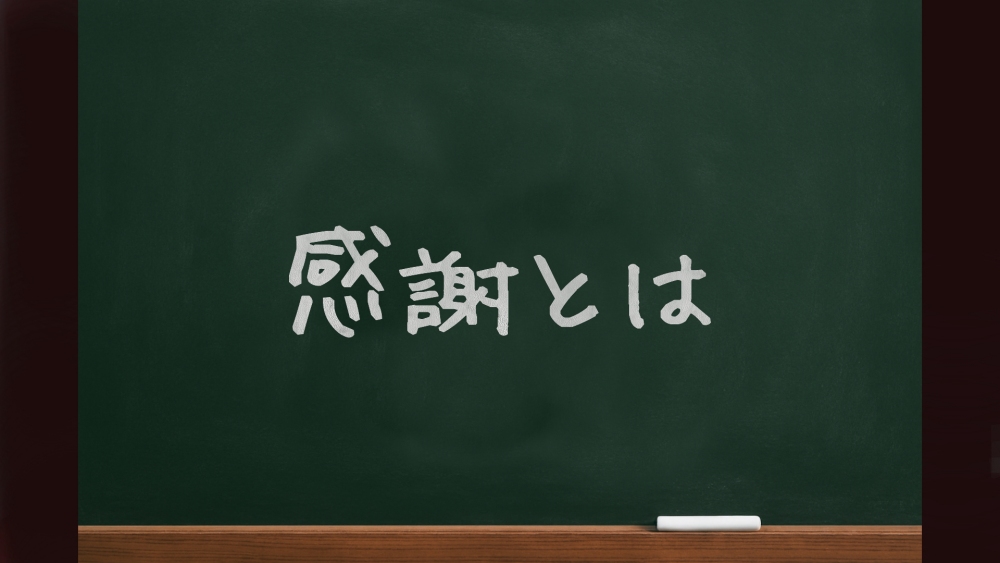





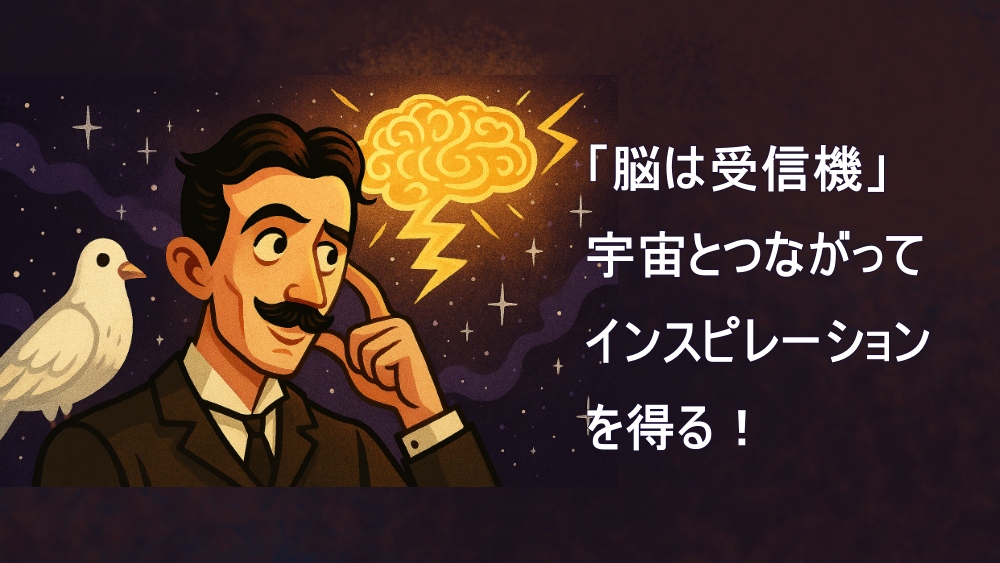
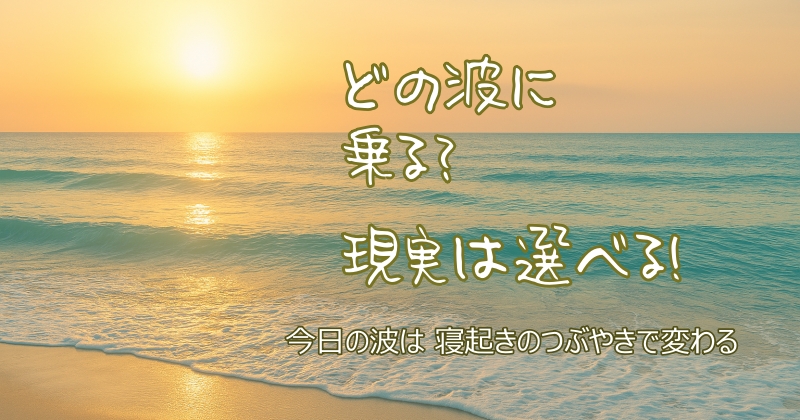
コメント